





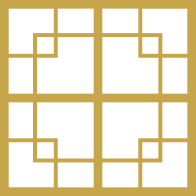
ここ最近急に気温が下がって寒い日があります。 急な温度変化に対応できずに体がしんどくなったり、不調が出やすい時期です。 風邪、マイコプラズマ、インフルエンザ、コロナ、胃腸炎など様々な感染症が流行ってきます。 自分はまだ大丈夫だけれど家族など周りの人がかかってしまったという方も多いと思います。 この時期「家族がかかってしまったのですが、何かできることはないですか?」「飲んでおくと良いものはありますか?」などの質問をお受けすることがよくあります。 家族がインフルエンザやコロナなどにかかってしまった時、看病をしたり睡眠が少なめになってしまうこともあり、さらに体調を崩しやすくなってしまい ・・・
腎の病気とは? 東洋医学でいう「腎」は生命の源、”先天の本”と称されています。 いわゆる生きていく上で一番大切な臓器です。 中国の書物では 腎の主な生理機能は精を蔵し、成長、発育、生殖及び水液代謝を司る。 また腎は骨を司り髄を生じ、その栄は髪にあり、耳と二陰(前陰と後陰)に開竅する。 腎の志は恐及び驚となし、液にあり唾となす。 足少陰腎経と足太陽膀胱経はそれぞれ腎と膀胱に属絡して、また腎と膀胱は水液代謝の面で直接関連しているので、表裏関係になっている。 と書かれています。 簡単にいうと「腎」は腎臓、膀胱、生殖機能、骨、耳、髪などに強く関わっています。 そして腎に関わる病気で言えば ・・・
11月に入り朝晩肌寒い日が増えてきました。 1日の中でも気温差があるので、服装でうまく調節するようにしましょう。 暑さが落ち着いて外出しやすい季節になったのですが、身体のだるさを感じる方がいらっしゃいます。 また、季節に関係なく普段から疲れやすいというお悩みもあります。 いつも疲れやすく、倦怠感が続いている 身体が重たい めまいがする事がある よく寝ても疲れが取れない 疲れているのに眠れない 食欲がない 胃腸がスッキリしない 浮腫みやすく身体がだるい 身体がだるくて気分も沈みがちになる 人によって症状は様々です。 東洋医学では、気血水のバランスが取れて ・・・
漢方の相談で良くお受けするお悩みの一つが大人ニキビ・吹き出物のご相談です。 大人ニキビは思春期を過ぎた20代以降にでき、一度治っても同じ場所に繰り返してできたり、生理周期に合わせてできることが多いという特徴があります。 思春期のニキビと大人ニキビの違い 思春期にできるニキビは皮脂の分泌量が多くなることで、おでこや鼻などのTゾーンにできることが多いです。 いっぽう大人ニキビはホルモンバランスの乱れや生活習慣、ストレスなど様々な要因が重なっていることが多く、治りにくい場合も多いです。 大人ニキビは頬やフェイスライン、口の周り、あごの周りなどのUゾーンにできやすいとされています。 ・・・
先日本屋さんに行ったときに「はたらく細胞の学べるクイズ」という本が積んでありました。 他にも「はたらく細胞」関連の本がずらっと並んでおり、思わず手に取って見てみました。 実は「はたらく細胞」という大人気のまんがで、NHKのEテレでも放送されていたり、12月に実写の映画の公開が決まっています。 以前テレビでチラッと見たことがあったのですが、「はたらく細胞」は体の中の赤血球や白血球、血小板などが擬人化され特徴的なキャラクターになっていて、細胞たちが外敵(ウイルスや細菌など)と戦ったり、日々体の中でどのような仕事をしているのかイメージしやすくなっています。 赤血球の女の子が台車を押しな ・・・
Category
日々の出来事
不妊漢方治療Q&A29 Q.ホットヨガは妊活に効果がありますか? A.ホットヨガは妊活にはおすすめできません。マイナスに働く可能性があります。 ホットヨガが妊活にいい、体を温めるので子宮機能が改善したり、ホルモンバランスが良くなるなどの記事をネット上で見かけます。 実際に妊活・不妊への効果をうたって営業されているお店さんもあります。 ただ東洋医学的に考えるとホットヨガは妊活におすすめできるものではありません。 というのもホットヨガは高温のスタジオでヨガを行います。 当然大量の汗をかくことになりますが、不自然な熱は体の余分な水分だけでなく、体の潤い「陰」 ・・・
風邪を引いて咳や痰が出て、それが長引いてなかなか治らなかったりする場合があります。 それが何カ月も続いて病院で検査しても特に問題がないのに、白っぽい痰が少しずつ出たりする方、または元々痰が出やすい体質の方は脾虚かもしれません。 脾虚というと胃腸系の働きをつかさどるため便秘下痢お腹の張りなどの消化器系の症状だけだと思われがちですが、脾は水分代謝にかかわるため、脾虚になるとむくんだり白っぽい痰がでやすくなったりもします。 他にも脾虚になると疲れやすくなったり、物をいうのがおっくうになったり、食後にすごく眠くなる、体調が悪くなるとむくむ、などの症状もあります。 脾虚に用い ・・・
Category
漢方相談
心配性というとネガティブなイメージばかりがありますが、良い面もあると思います。 色々なことについて大丈夫か不安になったり、特に自分や家族の体の健康についてすごく心配になってしまい、家族などからは心配しすぎだと言われてしまう方もいらっしゃいます。 ご自分でも心配しすぎかなぁと悩まれたりされることもあります。 けれどそういった方は、自分の体の声をきちんと聞くことができているとも言えると思います。 そして、なるべく体に良いことをしようと考えたり、良い方法はないか調べてみたりされる方が多いです。 適度に気楽に考えるのは大切なことですが、何も考えず好きなものを食べたいだけ食べ ・・・
9月も終わり10月に入りますね。 昼間でも涼しい風が吹いていたり季節が進んだなあと実感します。 真夏の蒸し暑さはなく過ごしやすい気候になっているはずなのに、なんか体がだるいという方も多いです。 夏の疲れが出ていたり、うまく体が気候の変化に対応できていないのもあるかもしれません。 東洋医学では秋の邪気を「燥邪」とよび、この乾燥の影響を最も受けやすいのが五臓の「肺」です。 肺は呼吸器系や皮膚、大腸の働きと関わりが深く、秋は空咳や皮膚のトラブル、便秘などのおなかのトラブルが出やすくなります。 秋に出やすい不調 呼吸器症状:空咳、のどの痛み、外に出しにくい痰、鼻水、鼻づまり ・・・
Category
季節の養生法TOP