





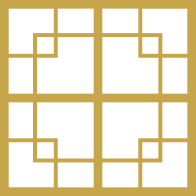
春は「肝」の季節と言われ、暖かくなり植物が芽生え、体の陽気が高まってきます。 それとともに心身の働きも活発になりますが、自律神経が過剰に働きすぎるとバランスが乱れ、自律神経の症状が現れやすくなります。 今年は気温が上がったり下がったりの差がとても激しく、初夏のように暖かくなったと思ったら寒波が繰り返し来たりと、寒暖差の激しい厳しい春でした。 そして今はもう初夏のような陽気。 体も心もついていけず、体力、とくに「心」の消耗した方がとても多い気がします。 漢方相談で来られている方にも、 色んなことが不安に感じる 落ち込みがひどく時に涙が出る やる気がでない 怖い夢、不快 ・・・
明日は全国的に夏日だそうです。 夏日とはその日の最高気温が25℃以上になる日をいいます。 今週初めも朝はまだ冷え込むなあと思っていたら、あっという間に夏日。 まさに冬から春を通り越して夏が来たみたいな感じですね。 急に暑くなり出すと、皆さん冷たいものを摂りがちです。 今日の朝、道端にアイスの包み紙が捨てられているのを目撃してしました。 自動販売機からもホットがなくなり、皆さん冷たいものを欲している様子。 とは言っても朝晩はまだ涼しく日中との気温差は10℃以上あります。 昼の暑さに騙され冷たいものばかり飲んだり食べたりしていると胃腸が冷え、GWを過ぎるころには胃腸が弱 ・・・
春は気温の変化が大きく、寒くなったり暖かくなったり、日によって大きな差があります。 春がくるのはうれしいけれど、体が気温差についていかないと言うお声もよく耳にします。 そして春は東洋医学では風邪(ふうじゃ)の影響を受けやすい季節です。 風邪は、漢方で病気の原因とされる6つの外因「風・寒・暑・湿・燥・火」のひとつです。 風邪(ふうじゃ)は体の上の部分に症状が出やすく、風のように変化が激しく、急に症状が出たりなくなったり場所が変わったりなどの特徴があります。 風邪(ふうじゃ)によるトラブルは色々ありますが、春は花粉症や肌荒れ・皮膚の痒みなどアレルギーの症状でお悩みの方が多くなりま ・・・
Category
季節の養生法
ここ最近急に気温が下がって寒い日があります。 急な温度変化に対応できずに体がしんどくなったり、不調が出やすい時期です。 風邪、マイコプラズマ、インフルエンザ、コロナ、胃腸炎など様々な感染症が流行ってきます。 自分はまだ大丈夫だけれど家族など周りの人がかかってしまったという方も多いと思います。 この時期「家族がかかってしまったのですが、何かできることはないですか?」「飲んでおくと良いものはありますか?」などの質問をお受けすることがよくあります。 家族がインフルエンザやコロナなどにかかってしまった時、看病をしたり睡眠が少なめになってしまうこともあり、さらに体調を崩しやすくなってしまい ・・・
9月も終わり10月に入りますね。 昼間でも涼しい風が吹いていたり季節が進んだなあと実感します。 真夏の蒸し暑さはなく過ごしやすい気候になっているはずなのに、なんか体がだるいという方も多いです。 夏の疲れが出ていたり、うまく体が気候の変化に対応できていないのもあるかもしれません。 東洋医学では秋の邪気を「燥邪」とよび、この乾燥の影響を最も受けやすいのが五臓の「肺」です。 肺は呼吸器系や皮膚、大腸の働きと関わりが深く、秋は空咳や皮膚のトラブル、便秘などのおなかのトラブルが出やすくなります。 秋に出やすい不調 呼吸器症状:空咳、のどの痛み、外に出しにくい痰、鼻水、鼻づまり ・・・
Category
季節の養生法
とても勢力の強い台風がきているということで、頻繁に携帯で気象ニュースをチェックしています。 すごく速度が遅いようですが、大きな被害がなく通り過ぎてくれることを祈っていますが心配です。 台風や雨がひどく降る前は、頭痛やめまいが起こりやすい方がいます。 急激な気圧や気温の変化が起こると、自律神経バランスがくずれ体がついていかなくなってしまいます。 また、台風や雨は多量の湿気を含んでいますので、漢方的に体に湿がたまりやすい方は、頭痛やめまい、肩こり、関節痛などがより起こりやすくなってしまいます。 いつもより体がだるい、倦怠感があると感じる方も多いですね。 そ ・・・
8月に入り、猛暑日が続いて体の負担が大きく体調を崩しやすい時期です。 暑さと湿気で寝苦しいため、なかなかぐっすり眠れないという方もいらっしゃると思います。 上手にエアコンを利用したり、体の余分な熱をとってくれる食べ物(キュウリ、トマトなどの夏野菜、スイカ、豆腐、緑茶、ミントのハーブティ)を取り入れるなどもおすすめです。 寝る直前に入浴すると熱が冷めなくてなかなか寝付けないという方は、布団に入る時間の1~2時間前に入浴を済ませておくのも良いと思います。 漢方薬で睡眠の質を良くするものには色々なものがあり体質や症状よって変わります。 熱がこもっている場合は冷ましたり、気 ・・・
まだ梅雨明けしていないのに連日暑い日が続いています。湿度が高く不快指数も高いため体がしんどいという方がとても多いです。 ニュースでも連日報道されていますが、最近の夏は以前とは変わってきて、若い人でも本当に気を付けて対策をしなければ、熱中症などで体調を崩しやすくなってきました。 夏を乗り切るのに何かおすすめのものはありますか?と言われることがたびたびありますので、いくつかご紹介しますね。 ◎松寿仙 クマザサ、赤松葉、朝鮮人参からできているエキス。 どんな体質の方でも飲めて、体の自然治癒力を高めてくれる。 また血流を良くしてくれるので、夏に心配な脳梗塞や心筋梗塞にもおす ・・・
6月も半ばを過ぎましたが今年は梅雨入りが遅い地域が多いですね。 大阪では週末から雨が続くようでようやく梅雨入りしそうです。 梅雨時期から夏にかけて起こりやすい不調があります。 軟便、下痢しやすい(時には下痢や便秘を繰り返す場合も)、お腹の張り、食欲不振、胃のもたれなどの症状が出やすくなります。 そして胃腸のトラブルとともに多いのが天気痛や気象痛とも言われる雨降りに起こる頭痛です。 また雨が降ると体が重く感じるといった方もいらっしゃいます。 近年は暑さが厳しく熱中症に注意しなくてはいけないので適度に水分補給は大切です。 でも冷たい飲み物を一 ・・・
Category
季節の養生法
雨が続くと鬱になる?やる気が出ない?~~原因と対策について 3月はほんと雨が多かったですね。 まるで梅雨のようでした。 そして雨が続いた今年の3月は、うつっぽくなったり、落ち込んだりやる気が出ないという症状が出ている方がたくさんいらっしゃいました。 雨が続くと鬱っぽくなったり、やる気が出ない原因は? ①湿度が高く体が重く感じる 雨が続くと湿度が高くなります。 そうすると体に余分な水が溜まっている方は体が重く感じやすく、だるく気分的にもふさぎがちになります。 日本は四方を海に囲まれているため体に水が溜まりやすく、近年は水分の摂りすぎや甘いものの過剰摂取で ・・・
TOP